なぜ政令指定都市の農振は動かないのか─制度・責任・まちづくりの迷路を解く

目次
制度が現実を映していない/農業振興地域という名の枠

政令指定都市では駅前や高速インターのそばなど、明らかに都市的な土地利用に移る地域にもかかわらず、農業振興地域(農振)として指定されたままというケースが散見されます。
実際に「駅前なのに農地」「インター横なのに農振だから売れない」という声を、長年この地で営農してきた所有者から聞くことがあります。
制度としての農振は、農用地等の確保や農業の健全な発展を目的に都道府県知事が地域を指定し、市町村がその下で整備計画を策定する構えが整っています。
しかし、政令指定都市では、交通網の発展・住宅や商業施設の建設・人口構成の変化など、土地利用の状況が大きく変わっています。
そしてその変化を制度が十分に反映できていないため、「農振だから」として転用も売却もままならない土地が残されているという現実があります。
このミスマッチを整理すると、主に以下の三つの構図になります。
1.土地利用の変化を想定していた制度設計が、実際の変化スピードに追いついていないこと。
2.「農地前提」という制度の枠が、都市用途に転換すべき土地と合致せず、用途変更・除外が進みにくいこと。
3.所有者・農家にとって「売りたい」「辞めたい」「転用したい」という意志があっても、制度によって選択肢が制限されるという心理的・経済的な縛りがあること。
住宅が建ち、商業店舗が入っている地域でも、「自分の土地だけ農振指定だから何もできない」といった声が少なくありません。
特に駅前や幹線道路沿いなど開発が進む地点ほど、制度の硬直化が顕著です。
都市的な価値と農地としての規制がねじれたまま維持されているこの構図を、政令指定都市は早期に見直す必要があります。
このまま制度を当初設計のまま維持していては、「地域の活力を逃す」「都市としての成長機会を失う」「農地の有効活用が阻まれる」という三重の損失を招く可能性があります。
次章では、この制度硬直の背景にある「責任の所在」「制度運用の実態」を掘り下げ、政令指定都市が取るべき具体的な改革の方向を示します。
誰が責任を取るのか/政令指定都市・県・国のたらい回し構図
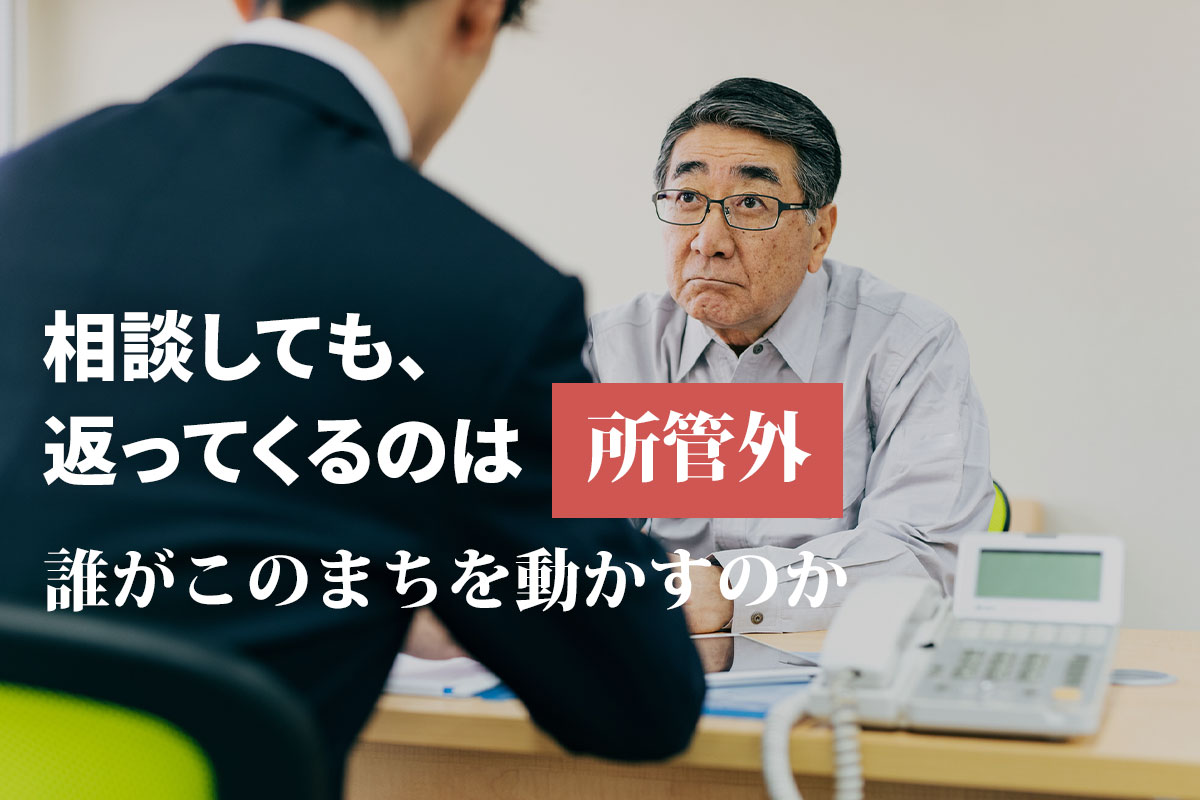
農地の現場では「制度が現実を見ていない」という不満が広がっています。
本来、農振制度は国・県・市の三層で支えられています。国が大枠を示し、県が基本方針を定め、市が実際の地域計画を立てる仕組みです。
書類上は整然としていますが、現場ではたらい回しが起きています。
市は「制度上の制限だから」と言い、県は「市の判断に委ねる」と答える。結局のところ、農家や土地所有者がどこに相談しても前に進まない。これが実態です。
行政の中では、こうした課題を把握している職員も少なくありません。ところが、制度を動かすことに慎重になりすぎ、誰も責任を取ろうとしない。
失敗を恐れる「減点の文化」が根強く残っており、改革の芽を自ら摘んでしまう構造ができ上がっています。
私は政令指定都市がまず果たすべきは「責任の見える化」だと考えます。
制度を所管する部署、協議を担う担当、判断を下す立場―それぞれの線引きを明確にし、市民や農家に分かる形で示すことです。
また、土地利用の見直しや農振の除外を検討する際は、県や国の判断を待つのではなく、市が主体的に意見をまとめ、調整を進める姿勢が求められます。
制度のたらい回しを断ち切るには、誰かが最初に動かなければなりません。政令指定都市がその役割を担い、責任をもって地域の声をすくい上げることこそ、農地と都市が共に生きる道を開く第一歩です。
都市づくりと農地保存のせめぎ合い/政令指定都市のまちづくりと農振指定のズレ

政令指定都市の郊外では、駅や高速インターの整備に合わせて住宅地や商業施設が次々と生まれています。
ところが、そのすぐ隣に「農振(農業振興地域)」の看板を掲げたまま、取り残された農地が点在しています。
この不自然な光景こそ、政令指定都市の制度が現実の変化に追いついていない証拠です。
農振制度は、かつて農業を守るために設けられたものです。しかし今の横浜においては、もはや「守る」という名の下で土地を縛りつける制度になってしまっています。
駅前で農業を続けられる人がどれほどいるでしょうか。インターの脇で車の排気を浴びながら農作業ができるでしょうか。
それでも市は「農振だから」という一言で片づけてしまう。この現実に、私は強い疑問を感じます。
横浜市の「都市農業推進プラン」では、高齢化や後継者不足、遊休化を課題として挙げています。
ところが、その原因の一部は行政の制度運用そのものにあります。都市化が進む区域で農振指定を見直さないまま放置しているから、結果的に農地が活かされず、
「もう農業はできないが転用もできない」という中途半端な土地が生まれているのです。
この状態を放置することは、市にとっても地域にとっても大きな損失です。都市として発展の機会を逃し、農地としても機能せず、結果的に人も金も動かなくなる。
これは単なる土地利用の問題ではなく、まちの生命線にかかわる問題です。
政令指定都市はまず、「農振=不変」という思い込みを捨てるべきです。駅前や幹線道路沿いなど、すでに都市化の波が明白な区域は、見直し対象として明示しなければなりません。
農地として続けるのか、都市として生まれ変わらせるのか、あるいはその中間の形を模索するのか。選択肢を開くことが、行政の責任です。
また、農政と都市計画が別々に動いている現状も改める必要があります。
現場を知る人間が同じテーブルで議論し、地域の将来像を共有する―その仕組みを市が率先してつくることです。「誰も動かない」ではなく、「市が動く」構造に変えなければ、このまちの土地は未来を失ってしまう。
農地を守ることは大切です。しかし、守るとは「動かさないこと」ではありません。本当に守るべきは、土地の価値と地域の暮らしです。
政令指定都市がその視点に立ち戻るとき、初めて「農振の見直し」はまちづくりの希望になるのです。
動かない行政文化と現場の苛立ち/政令指定都市職員に求められる覚悟
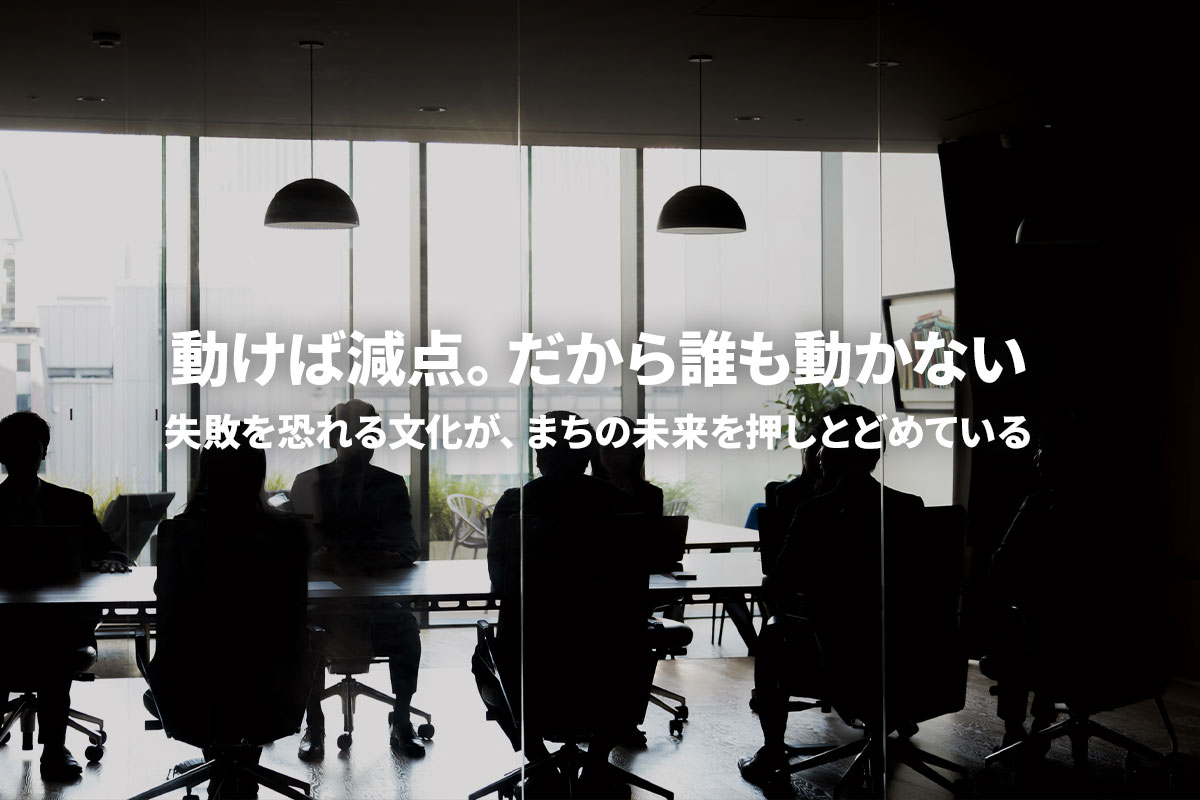
政令指定都市の行政には、制度の課題を理解していながらも、誰も動かそうとしない空気が漂っています。
それは怠慢ではなく、「動くと減点される」という文化が根づいてしまっているからです。制度を変えて失敗すれば責任を問われ、成功しても評価されない。だから結局、誰も手を出さない。
この減点主義こそが、現場を止め、まちづくりを遅らせている最大の病だと私は考えています。駅前やインター沿いのように、変化が激しく、判断が求められる場所ほど、市の対応は慎重になりすぎています。
相談に行っても、「制度上できません」「県の判断です」「まず組合を作ってから」といった言葉で終わってしまう。
これでは現場の声が制度の外側で空回りするだけです。農地も地域も、行政の机上で時間を浪費しているようなものです。
私は政令指定都市がこの悪循環を断ち切るためには、まず「責任の所在」と「評価の仕組み」を変えるべきだと思います。
職員が挑戦すればきちんと評価される、失敗しても再挑戦が許される。そんな組織でなければ、本当の改革など起こりません。部局を越えて課題を共有し、現場の声をもとに改善を重ねていく―そうした仕組みを市として正式に制度化するべきです。
制度をつくるのも人、動かすのも人です。どんな立派な計画を掲げても、現場を見ず、責任を避ける文化のままでは何も変わりません。
私は政令指定都市の農政・都市計画・土地利用を担う職員一人ひとりにこそ、「自分が変える」という意識を持ってほしいと願っています。
このままでは、駅前や幹線沿いの農地は、地域の未来を支える資産ではなく、誰にも手が出せない空地のまま朽ちていく。
制度・責任・文化――この三つを同時に見直す時が来ています。政令指定都市がその覚悟を持ち、まず一歩を踏み出すこと。それが、このまちの農地と都市をもう一度動かす唯一の道だと、私は信じています。


